たまにはサッカーの話をするかな?
「最近のお前の話は美術や音楽ばかりだ」と友人に言われてしまったので、たまにはサッカーの話をしようかな?、とおもいます。 まずは、浦和レッズのアジアチャンピオン!おめでとうございます! (浦和はボクのルーツなので嬉しいです!)...


狼を見に行く
晩秋の一日、運慶は見損ねたが、オオカミの石像を見に行くことにした。 何故オオカミなのか?を説明するのはメンドウなのだが、立体造形も仕事としておこなっている身としては、ちょっとでも気になる造形物は自分の目で「見ておきたい」のである。城峯神社の狛犬がオオカミであって、なかなかの...

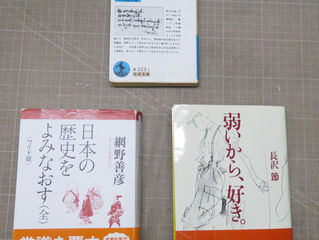
10月の終わりに
先週の月曜日に左足を手術した。 「たいした手術ではない」と、医者に言われて安心し、全身麻酔し、手術を受けたのだが、実際には手術後に痛い目にあった。 毎日足が痛いのです。じんわりと、しかし、明らかに痛いのです。おかげで、この1週間あまり、寝たり起きたりの老人的日々。。...






















